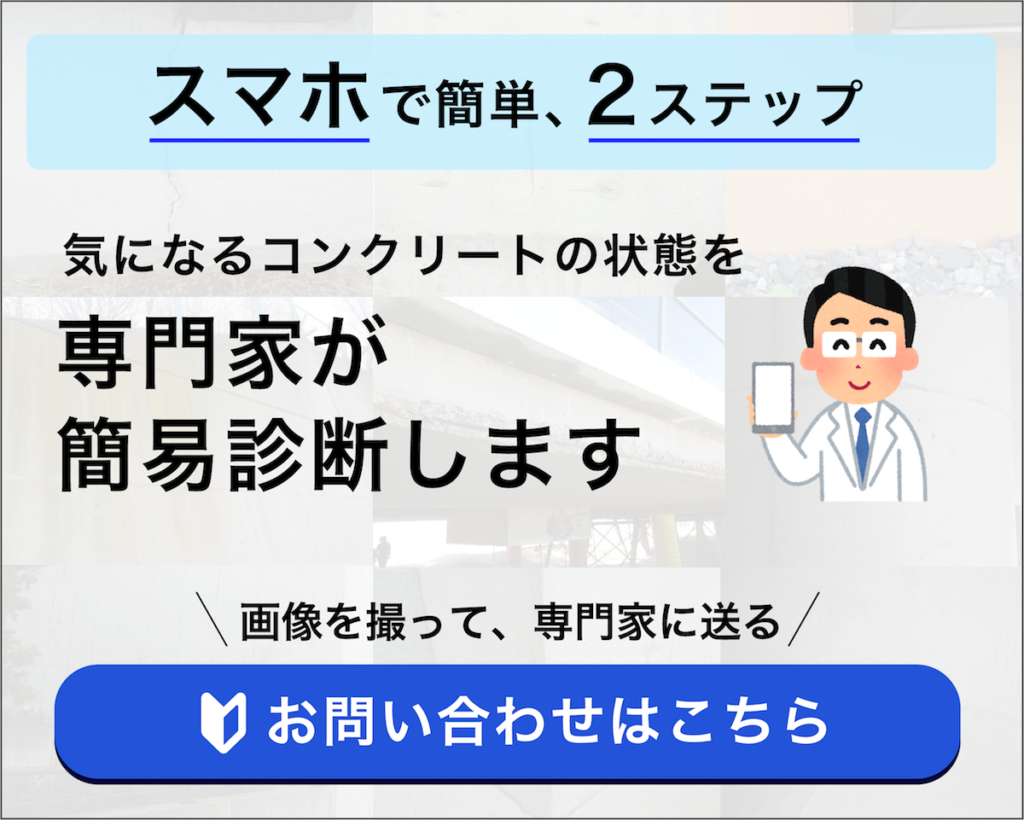コンクリートのすりへりとは、コンクリートの表面を水が流れたり、車などが走行することによる摩耗作用や衝撃によって、コンクリートの断面が徐々に減少していく劣化です。
コンクリートのすりへりには、舗装面のすりへり、床面のすりへり、ダムや水路に見られる砂などによるすりへり、海氷などによるすりへりなどの様々な事例があります。
この記事でわかること
1. コンクリートのすりへりとは
コンクリートのすりへりとは、コンクリートの表面を水が流れたり車などが走行することによる摩耗作用や衝撃によって、コンクリートの断面が徐々に減少していく劣化です。
コンクリートのすりへりには、車輌の走行による舗装面のすりへり、フォークリフトなどの移動による床面のすりへり、ダムや水路に見られる砂礫やキャビテーションによるすりへり、海氷などによるすりへりなどの様々な事例があります。
2. メカニズム
コンクリートのすりへりは、下記の3段階で進行しています。
- コンクリート表面に近いモルタル層がすりへる。
- 表層部(モルタル層)がすりへった後、砂利(粗骨材)が露出し砂利自体がすりへる。
- 砂利(粗骨材)が剥離。
コンクリートの強度が高い場合、コンクリートが緻密になるため進行速度が遅くなります。
すりへる原因は、様々あるため分類を分けてご紹介します。
2-1. 舗装路面のすりへり
舗装路面のすりへりは、通行する車両の形式、重量、速度、車輪などが原因で発生します。
通行する車両によってモルタルと骨材が一様にすり減った場合、舗装面が平滑になり路面の摩擦抵抗が低下するため、車両の制動に支障をきたす可能性があります。
また、タイヤチェーンを装着した場合、タイヤの走行部分のみ大きくすりへります。その結果、舗装面にわだちができ、騒音や水はねの原因となります。
2-2. 床面のすりへり
工場や倉庫など床面をフォークリフトなどが走行する場所では、その車両の重量、速度、床面の状態が原因ですりへりが生じます。
このすりへり現象は、2つの接触状態によって生じます。
①アブレイジョン(切削)摩耗
床面とタイヤなど2つのものが接触すること原因発生
②アブレイジョン(切削)摩耗と押し込み作用による表面疲労摩耗が複合
床面とタイヤなどの間に石などが入り込み3つのものが接触することが原因で発生
床面のすりへりには表面の硬さ重要であるため、すりへり抵抗性のある材料を選定することがすりへりを防止する上で大切です。
また、屋上に使用される防水層は、車両走行によるすりへりが多く発生しています、そのため、使用する際は注意が必要です。
2-3. 砂礫によるすりへり
ダム、水路、排砂路など構造物において、砂礫を含む水が流れることによって発生します。水が流れるだけであれば、流れが速くてもすりへり現象はほとんど発生しません。
このすりへり現象は、舗装面や床面のすりへりとは異なり原因が複雑です。
そのため、劣化予測をするのが難しいのが現状です。水路であれば、流速毎に鉄筋のかぶりを増す対策をとっています。
2-4. キャビテーションによるすりへり
凹凸や急激な屈曲をもつコンクリートの表面にそって、流速の速い水が流れる場合や、障害物などによる局部的な圧力降下も加わると、下流側に空洞が発生しその部分は水蒸気の気泡が混在した状態となります。
この水の流れが圧力のやや高いところに移動すると、水蒸気の気泡は急激に圧力がかかり潰れ、コンクリート面に大きな衝撃を与えて、ピッチング損傷を与えます。
キャビテーションによるすりへりは、激しく集中的であるため、長期的な浸食作用に対して抵抗することはできません。
2-5. 海氷などによるすりへり
海氷(かいひょう)のすりへりは、砂、氷、波などの物理的な作用により発生します。
具体的には、砂の研磨作用による海中部の摩耗、氷の移動に伴う潮汐帯のすべり摩耗、波力と凍結融解および塩化物作用による飛沫帯の劣化による摩耗が原因です。
氷による摩耗は、氷がコンクリート表面を1㎞移動すると0.05㎜摩耗すると言われています。
3. 劣化の特徴
すりへりの劣化は、コンクリートの断面減少がほとんどです。鋼材の露出や腐食・断面欠損にまで進展しますが、そのような状態にまで放置されるケースはほとんどありません。
その他には、コンクリート表面が荒くなるため、流速の低下が起こります。
コンクリート表面のモルタル部がすりへり砂利がむき出しになっている状態のため、美観の問題もあります。
4. まとめ
すりへりは、コンクリートの強度、車両走行の状況、水の流速や土砂の混入状態、波の強さや頻度、衝突の有無などによって進行具合が決まります。
コンクリートの水セメント比が小さいほど緻密で強度が高いため、すりへり速度が遅くなります。
すりへりが発生した場合、その部分を補修することが基本です。しかし、何が原因ですりへっているのかを把握しないで補修した場合、適切な材料でないためすぐに再劣化を起こす可能性があります。
すりへりを発見した場合、コンクリートの専門家にご連絡下さい。